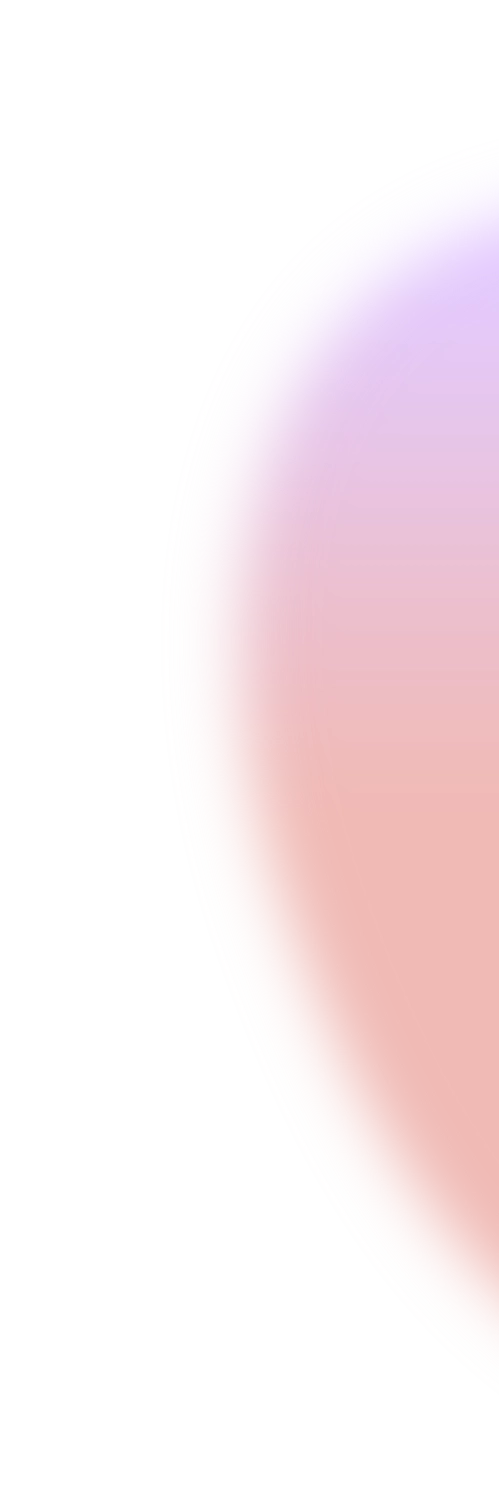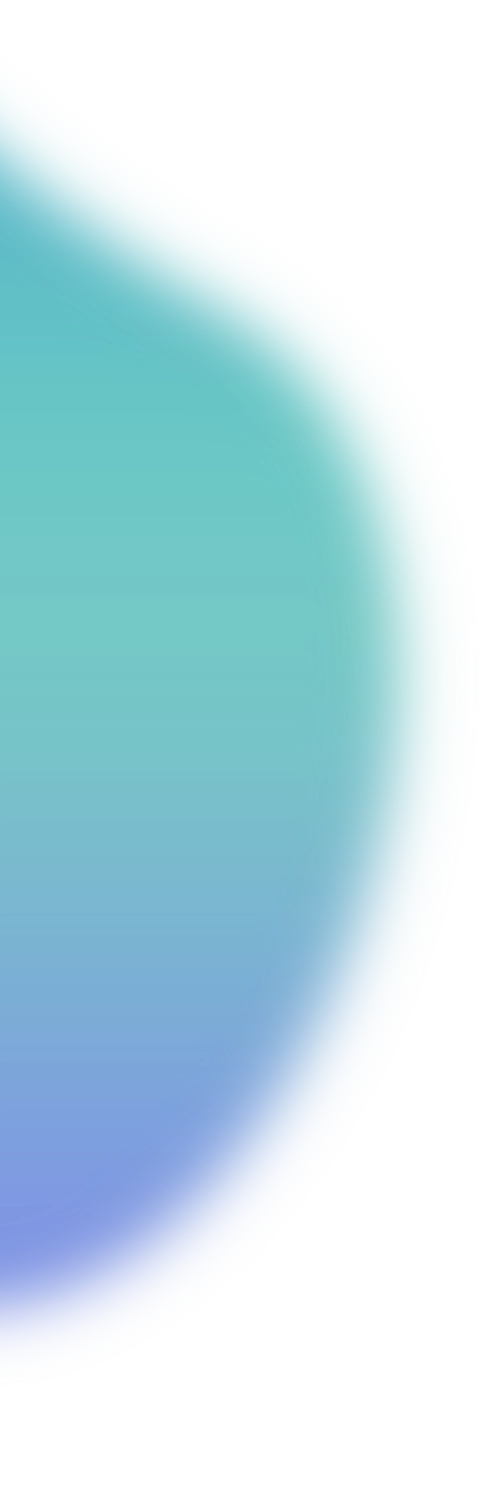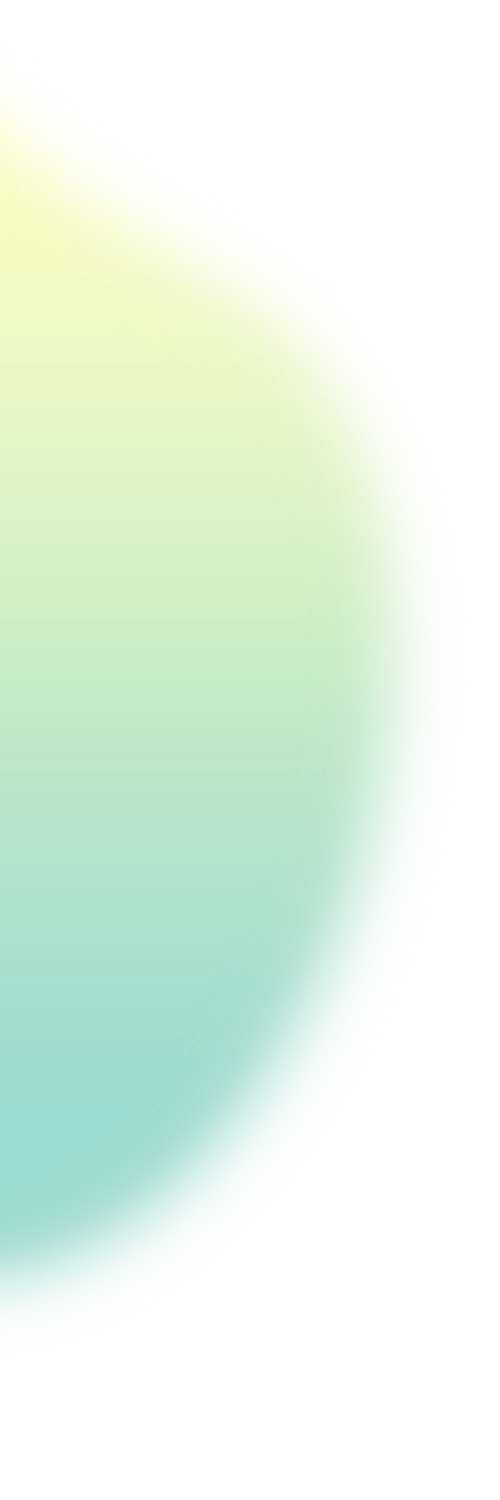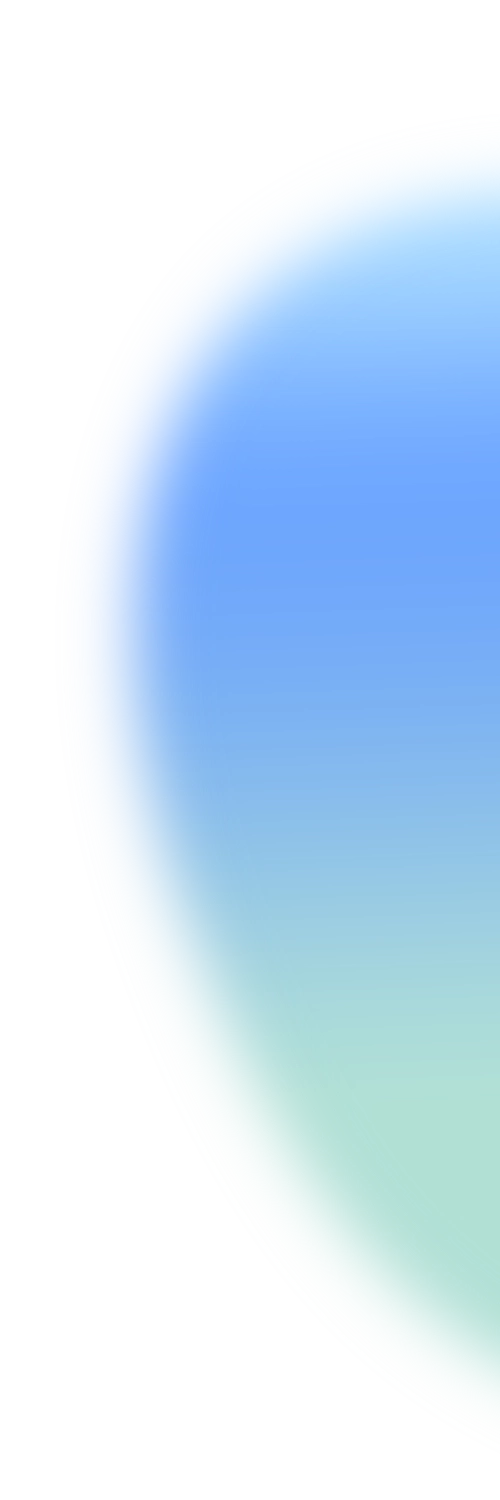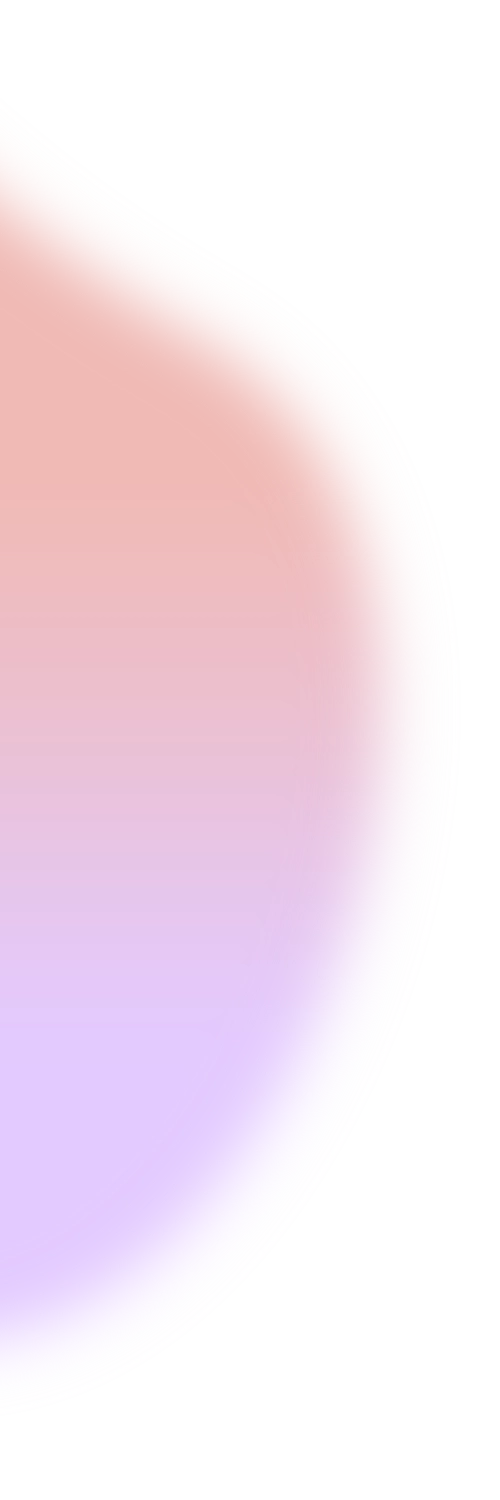The History
of the Fluid Division
これまでの流体事業部


流体事業のあゆみ
新明和工業の流体事業は、1954年5月に自吸式エンジンポンプの初号機を完成させたことから始まりました。
70年間の歴史は、戦後に集まった仲間たちがゼロから新しい挑戦をし、試練を乗り越えてきた歴史です。
年代
- ●1950
-
ポンプ第1号の誕生
新明和工業の流体事業は、1954年5月に自吸式エンジンポンプの初号機「ポインター・シャイナー」を完成させたことから始まりました。
戦後に集まった仲間たちがゼロから新しい挑戦をし、流体事業はスタートを切ったのです。自吸式ポンプの初号機が試作に成功した後、さらなる改良を重ね、1955年には自吸式ポータブルポンプ「ポインター」の量産を始めました。そして、営業部門を設立し、本格的な営業活動をスタートさせました。営業チームや設計、製造のスタッフは、各地で「ポインター」を使って、マンホール内にたまった水を排出するデモを行いました。その結果、当社の製品が当時独占状態にあった他社製品よりも高性能であることを認められ、採用され始めることとなったのです。
 草創期Early period
草創期Early period - ●1960
-
自吸式ポンプで業界トップへ
自吸式ポンプの販売が好調になると、他の競合製品も次々と登場してきました。
こうした販売競争に勝ち抜くためには、ユーザーのニーズに応えて新しい機種を増やすことが重要でした。
そこで、私たちはさまざまな用途に対応するために、30~40種類ものポンプを開発しました。
この努力が実を結び、1963年頃には、当社は自吸式ポンプの分野で業界のトップと称されるようになりました。
-
水中ポンプへの道を拓く
自吸式ポンプのおかげで、私たちの事業は徐々に軌道に乗り始めました。
しかし、まだまだ安心できる状況ではありませんでした。事業をさらに確立するためには、次の主力製品が必要です。その鍵となったのが、水中ポンプの開発でした。私たちは自吸式ポンプから土木用の水中ポンプ、そして設備用の水中ポンプへの方針転換を進めました。この時期に急成長していた水処理プラントメーカーを通じて、し尿処理場や大手企業の廃水設備、コミュニティプラント、建築設備の排水用に多く採用され、売上の拡大に大いに貢献しました。


- ●1970
-
確立期Establishment
period本格的な工事事業の展開
1973年、ポンプ工事課(現:システム本部)が設置され、雨水排水ポンプ場等の設計、施工を行うようになりました。当時わが国初の省エネ型制御方式のポンプ場へ、据付が簡単な新明和水中ポンプと液面制御スイッチを使った輪番起動の方式を納品するなど、雨水排水ポンプ場への大型ポンプの納入を増やしていきました。
1979年には当時の流体製品の生産拠点であった宝塚工場へ、ポンプの大型化に対応するための試験水槽を完成させ、口径800mm、110kWの大型ポンプの製作に対応できるようになりました。

-
水処理機器市場へ参入
1975年、大型の下水関連工事を受注しました。
このプロジェクトは非常に大規模なものでした。
さらに1977年には、ハニカム式回転ばっ気装置「ハニーローター」をはじめとして、下水処理場のごみ詰まりを解消するスクリュー式除塵機や、水面の浮遊物を回収するフロートポンプを発売しました。また、同年には業界初となる「立型水中ブロワ」を発売しました。ブロワの製造メーカーとしては新参者でしたが、私たちの製品は水処理プラントメーカーに採用され、水処理の重要な役割を果たす存在となっていきました。

- ●1980
-
回転機グループの発足
1982年頃から、新製品の投入や海外販売を行っていたものの、下水道予算の停滞や景気の悪化により、流体事業の業績は伸び悩んでいました。そこで、流体事業部門をより柔軟な組織に再編成し、1985年10月に回転機グループを設立しました。
このグループは、設計、資材、営業、組立、品質保証の各部門から約70名が集まりました。
その後、景気が回復し下水道予算も増加したことで売上は上昇。1986年には回転機課に、1989年には回転機部に拡大し、流体事業の存在意義は高まっていきました。
- ●1990
-
小野工場の設立と立ち上げ
「流体製品を存続し、拡大させるため」という目的のもと、1992年、回転機専用の工場「小野工場」を設立しました。1994年には、各営業所に分散していた全国の製品在庫を、小野工場での一元管理へと変更し、さまざまな検討を経て、品質向上とリードタイムの短縮を実現しました。
 拡大期Expansion
拡大期Expansion
period -
ポンプシステム本部の設置
1993年、私たちの会社はマンホールポンプ市場の拡大を見越し、官公庁向けの営業に力を入れることを決定しました。この新たな取り組みを実現するために、ポンプシステム本部(現:システム本部)を設立し、より専門的な組織を構築しました。この時期から、私たちは顧客の真のニーズを把握するための動きにシフトしていきました。
特に注目すべきは、「マンホールポンプ場無人監視システム」の開発です。この製品は、ポンプシステム本部の発展に大きく寄与する画期的な成果となりました。

-
新製品の開発ラッシュ
1995年から2000年にかけて、私たちの会社では新製品の開発が相次ぎました。その中でも特に注目すべきは、1995年に発売した、浄化槽向け樹脂ポンプ「NORUS(ノーラス)」です。強靭、軽量、防錆を兼ね備えた水中ポンプとして、開発された後も改良を重ね、今もなお主力製品の一つとなっています。
 発展期Development
発展期Development
period -
生産効率向上へ
小野工場では、材料費を抑えたり、組立ラインのレイアウトを見直したりすることで、製造にかかる時間を減らす取り組みが進んでいました。その結果、少しずつ成果が出てきました。1996年頃からは、事務所内にパソコンが普及し、電子メールシステムも導入されました。この流れに合わせて、さまざまな業務でOA(オフィスオートメーション)化が進みました。また、設計業務でも3次元CADが導入され、情報化時代の到来を感じさせるようになりました。

- ●2000
-
名誉ある賞を相次ぎ受賞
流体事業は「お客様に信頼され、喜ばれる製品を創る」という品質方針を追求し、市場の期待に応える製品を多数開発することに成功しました。その結果、製品の性能と品質が高く評価され、さまざまな賞を受賞しました。2008年2月には、中速水中ミキサー「SMMシリーズ」が優秀省エネルギー機器表彰の「日本機械工業連合会会長賞」を受賞。
さらに同年5月には、高効率・高通過性の水中ポンプ「CNWシリーズ」が「ターボ機械協会賞(技術賞)」を受賞し、2009年2月には再び「日本機械工業連合会会長賞」を獲得しました。これらの受賞は、私たちの製品の性能の高さを証明するものとなりました。


- ●2010
-
流体事業部への独立
2012年4月には、産機システム事業部から流体事業が「流体事業部」として発展的に独立を成し遂げました。
同年5月には、小野工場設立20周年を迎えました。
流体事業
生活環境を守り、支えるために、
水環境の循環や水害対策に貢献しています。 -
省エネルギーへの貢献
流体事業は社会的課題であった、24時間365日稼働する下水処理や工場排水処理関連機器の省エネルギー化に貢献するため、2012年より「民間向けターボブロワ『MAXシリーズ』」を、2016年より「官庁向けターボブロワ『STXシリーズ』」の販売を開始しました。
更に2016年10月には、当社従来機比最大40%の省エネルギー化を実現した「高効率水中ミキサ『SMEシリーズ』」を販売し、2018年2月に流体事業では3度目の優秀省エネルギー機器表彰の「日本機械工業連合会会長賞」を受賞しました。
- ●2020
-
浸水災害対策への貢献
局地的集中豪雨(ゲリラ豪雨)などによる浸水災害の対策として、流体事業は積極的に製品ラインナップを拡大しました。例えば、水没すると機能を停止してしまう陸上ポンプから、水陸両用ポンプである「立軸槽外型(耐水型)ポンプ」に置き換えることで、水没しても継続運転が可能となります。新明和の技術が災害対策の一助となっています。

-
海外市場の拡大
東南アジアの市場開拓を見据え、2020年にタイ王国へ新たに生産拠点を設立しました。更にターボブロワの拡販に向けて2021年には韓国のターボブロワメーカ「TurboMAX社」をグループ会社に迎えるなど、海外市場を拡大すべく流体事業部一丸となって取り組んでいます。